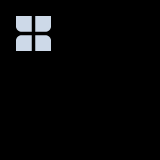検索結果
4104件のアーカイブスが見つかりました。
条件: 渇水
文化14年の干ばつ

文化14年(1817)5月から7月にかけて、大干ばつとなった。二頭出水は通常は下流の三吉田村(上吉田村、下吉田村、稲木村)の水田を養っているが、大池が干上がると善通寺領の要請に要請により、輪番で取水する慣行となっていた。この時も寺領側が上吉田村に二頭出水からの... 続きを読む
文化14年の干ばつ
文化14年(1817)4月から8月まで日照り続く。大社から小社に至るまで雨乞い祈願。鵜足郡で一番やけたのは岡田上村で、二番は造田村。内田下所免は一帯に稲が枯れ収穫なし。秋から飢人が出て、お上に救援の願いを差し出す。 郡内の難渋民に、古米120石が貸し付けられる... 続きを読む