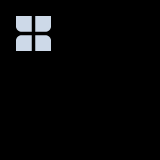検索結果
902件のアーカイブスが見つかりました。
条件:徳島県 土砂災害
安政元年の地震
安政元年(1854)、大地震。相生村では、伝聞として「山へ木を拾いに行っておった女子供は揺られて地上に倒れ叫ぶもあれば、猪垣が崩壊して、その石が四方へ転げるのもあった。山腹の田などは破れてさげること数十か所以上百か所もあり三日三晩ゆりつづいた」という話が残され... 続きを読む
安政元年の南海地震による善徳の地すべり
安政元年(1854)、安政南海地震により、善徳の地すべりがあったと言われているが、記録に乏しく、その規模等の詳細は分かっていない。この研究では、過去の南海地震の斜面災害について歴史資料及び現地調査に基づき、南海地震の斜面災害の特徴を報告している。 続きを読む
嘉永2年の豪雨
嘉永2年(1849)、豪雨があり、七日七夜降り続いたため、東馬場上方の大佐古山で山潮が起こり、丸岡(まろおか)に向かって走り、幅8軒(14m余)にわたり畑が押し流されたと言われる。 続きを読む
弘化5年の長雨・大雨
弘化5年(1848)2月より毎月雨が降り続き、1ヶ月に4、5日晴れるくらいである。このため、不作で人々は困窮した。6月上旬より大雨が降り続き大水となり、山崩れがあり、山林が破損している。当年は、夏の麦等は不作であったが、秋は豊作となった。しかし、8月の大風雨に... 続きを読む
天保14年の洪水・山崩れ
天保14年(1843)、大雨による大洪水、山崩れ、堤切れなど破損箇所が多く、田地が埋まった。この上、8月から9月にわたり長雨があり、立毛部が生え凶作となった。 続きを読む
天保13年の洪水
天保13年(1842)、馬路川で大洪水。これを「寅年の大洪水」と言い伝えている。洪水により白地馬谷の土砂が北名の数戸を埋め、水路は北名の北端を迂回して住吉山の麓に出た。馬路深川谷の堂床の大木が山津波に乗って立ちながら土居の田の中に押し出された。宮の谷の洪水は境... 続きを読む